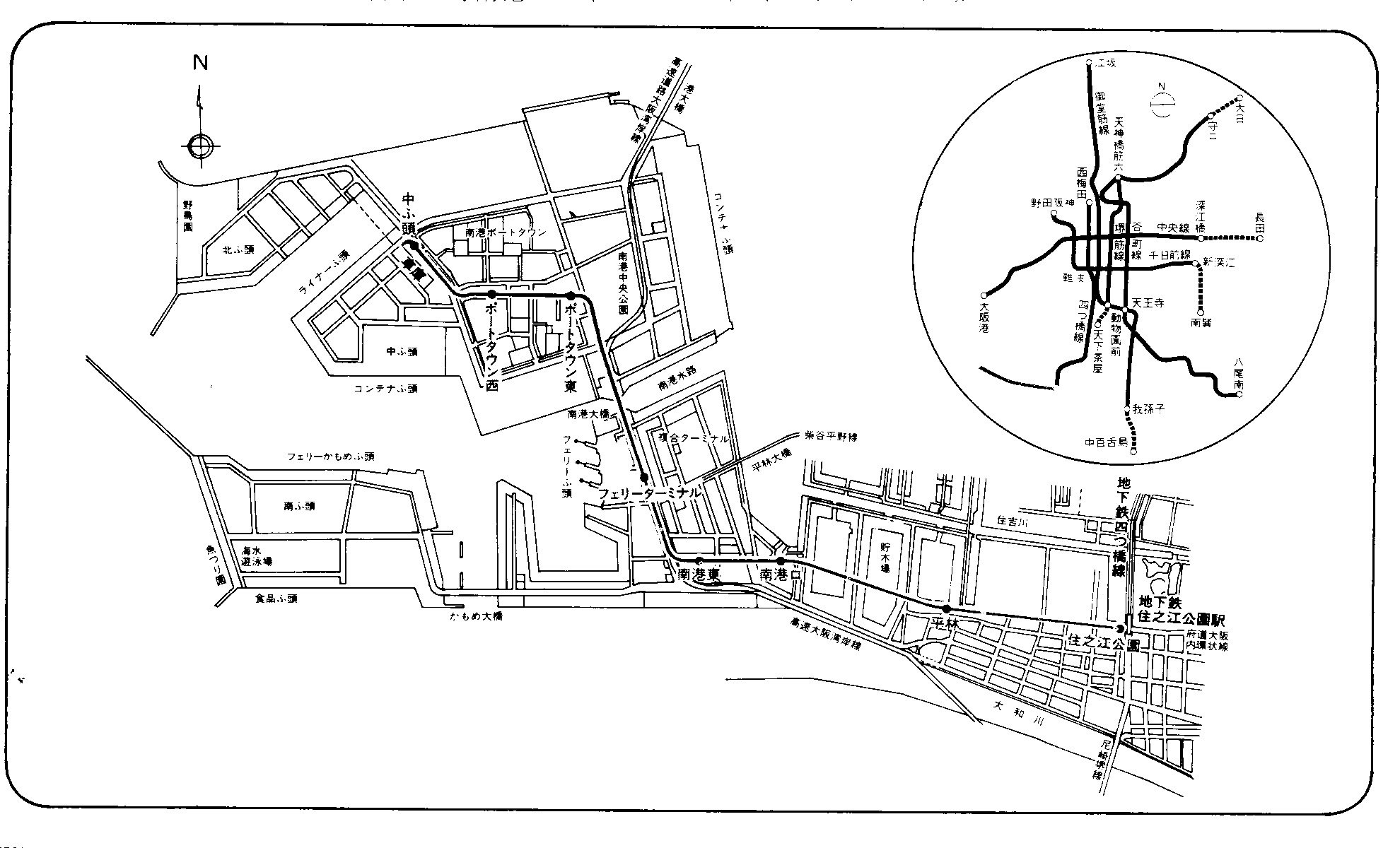
大阪市交通局
南港ポートタウン線
ニュートラム
佐藤信之
今回は、神戸新交通のポートライナーと同時期に計画され、営業を始めた、大阪市交通局のニュートラムを取り上げる.ガイドウェイをタイヤ走行する中量輸送機関の最初のケースであり、その後の新交通システムの先駆けとなった。
また、建設省の都市モノレールに対するインフラ補助制度を新交通システムに拡大する契機を作ったという点でも注目される。
前史
大阪市では、昭和45年に大阪北郊の千里が丘で開催された万国博覧会の開会に間に合わせるために、急ピッチで地下鉄が建設された。そのための巨額の建設費で、交通局の経営は相当厳しいものとなっていた。しかし、依然として都心部の交通改善のために新線の建設が求められた.そこで,地下鉄に比べて建設費の安い新しい交通機関に着目した。
昭和45年3月、大阪市公営企業審議会は、当時各メーカー乱立して開発が進められていた新交通システムの検討を求める答申を提出。交通局は5月20日新種交通機関調査委員会を設置して、調査検討を開始した。7月には「モノレールに関する調査研究報告書」が報告されたが、そこではモノレールを都市交通機関として採用することはおおむね可能という判断が示されていた.さらに、翌年には都市交通審議会答申第13号で、地下鉄1号線の輸送力が限界に近づいているため、並行路線の整備が緊急必要事として示された.これを受けて新交通システムの導入について検討することになり、昭和47年3月に「新交通システムの調査に関する報告書」がまとめられた。その内容は、都心部の路線では地下方式をとらざるを得ず、建設費が相当多額になり、経営面で困難な事態が予想されるというものであった。また、いずれの方式も開発途上にあり、かなりの問題点を含んでいるとしていた。
昭和48年にかけて、高架方式の新交通システムについても研究を行ったが,結局実現することはなかった。
なお、都心部の交通改善への新種交通機関の採用は、後にリニア方式によるミニ地下鉄という形で長堀鶴見緑地線として結実したわけであるが、いずれ取り上げたいテーマである。
ポートタウン線計画
大阪南港は、臨海工業地帯として大阪湾を埋立てて造成した930haの土地である。昭和33年に造成に着手したが、その後の社会情勢の変化で、阪神工業地帯の中心に位置するという立地条件から貨物需要が大きく増加したのに対応して、コンテナ埠頭、フェリー埠頭などの港湾施設の整備が進められた。昭和52年9月現在、その72%が完成していた。
昭和47年ころ、大阪市港湾局は、大阪南港の近代化と再開発計画を発表した。近代的な港湾・物流施設を整備して計画地を転用して、100haの大規模住宅地「南港ポートタウン」の建設を決定した。昭和50年には住宅建設に着手し、昭和52年から入居を開始して、昭和65年には4万人の人口を予定していた.別に南港口地区の再開発による人口5,000人の住宅地の計画があり、また周辺地域での従業人口は57,000人が見込まれた.
そこで、地域内の交通整備が急務とされたが、とりあえず昭和46年7月に、市営バスの運行を開始。11月9日には地下鉄四つ橋線の玉出〜住之江公園間を延長開業して、都心へのアプローチを確保した。さらに、この地域の足として、新交通システムの導入が検討されることになった。
昭和49年1月大阪市の総合計画局、土木局、港湾局、交通局が共同でプロジェクトチームを結成。さらに9月には国の調査費補助を得て、国、大阪府、大阪市、学識経験者による「大阪南港新交通システム調査委員会」を発足した。そして、50年3月に大阪南港新交通システム計画調査報告書を発表することになるが、そこでは軌道の建設費が安く、無人化で労働コストが削減できる新交通システムが適当という内容であった。また、時間帯によって編成両数を変化できるということで、需要に柔軟に対応できることも利点として指摘した.需要規模についても、予想される5,000人〜15,000人規模では地下鉄では過剰でありバスでは不足であるとし、中量輸送機関である新交通システムが支持された。この報告書では、さらに北側からも同様の輸送力を持つ交通機関の整備が指摘されており、これが大阪港からの新交通システムの整備計画につながる.(拙稿「大阪港再開発計画と新交通システム」『鉄道ジャーナル』31巻1号、1997年、に詳しい。)
当時開発中の多くの新交通システムの中で、どの機種を採用するかという大きな問題があった。昭和49年9月大阪南港新種交通機関機種選定委員会を設置。すでに開発が進んでいる
側方案内方式−KCV, KRT, NTS, PARATRAN
中央案内方式−MAT, MINIMONORAIL, VONA
の 7種類が検討対象となった。昭和52年2月7日には、大阪南港新交通システム機種選定報告書がまとめられ,大阪南港で導入する機種としてKCV, KRT, NTSが適当と結論付けていた。そして、昭和52年12月6日までに採用機種を、新潟鉄工所、住友電工、東洋電機によるNTSに決定した。
アメリカのVOUGHT社と技術提携して開発したもので、すでに同種の交通機関がダラス・フォートワース空港内で実用化していた。
インフラ補助制度の適用
新交通システムに対する国庫助成について、運輸省は、初期投資が大きいにもかかわらず対象とする需要規模は小さく、スケールメリットが期待できない。しかし、無人化を指向する新しい交通機関の先駆的プロジェクトであるため、国と自治体による助成が必要であるとした。
運輸省の検討した助成制度は、日本鉄道建設公団が車両を除いた施設を建設し、交通事業者に対して25年間元利均等割賦で譲渡するというもの。国と自治体は公団に対して、当初10年間の利子全額を補給するこことし、その補給額の2/3を国、1/3を自治体が負担するとした。
これに対して、建設省は、すでに制度化されている都市モノレールに対するインフラ補助と同一制度の適用を検討した。
当初、昭和50年度での予算化を目指していたが,結局実現せず、昭和50年11月大阪市長は国庫補助制度の確立について陳情書を提出した。その結果、12月28日運輸、建設両省による「新交通システムに関する覚書」のなかで、昭和51年度から両省で「新交通システム経済性調査委員会」を発足させて、将来の建設助成について検討することが示された.
この覚書にもとづいて、建設省は昭和51年年度当初予算に、国庫補助費(モノレール道整備費補助)を計上。その上で両省間で検討が続けられた.そして、昭和52年1月18日運輸、建設両省は、「新交通システムのインフラ部分は、港湾整備事業と街路事業で道路インフラ方式により整備する」との覚書が結ばれ、新交通システムに対するインフラ補助制度が創設された。5月10日には、適用法規について運輸、建設両省間で調整の結果、建設省の管轄区間については軌道法、運輸省については地方鉄道法を適用することで合意する。
ポートタウン線の建設
地下鉄四つ橋線住之江公園を起点に大阪南港の中ふ頭までの営業キロ6.6km複線の側方案内方式新交通システムである。この路線のうち、住之江公園〜フェリーターミナル間は都市街路事業として軌道法、フェリーターミナル〜中ふ頭間は港湾整備事業として地方鉄道法が適用された。
住之江公園からポートタウンまで府道大阪内環状線の中央分離帯に高架橋が建設されるが、その内、フェリーターミナル付近は3層構造の高架橋が建設されて、その最上部には阪神高速道路大阪湾岸線が入り、その下の中層部に新交通システムの走行路が設けられることになった。
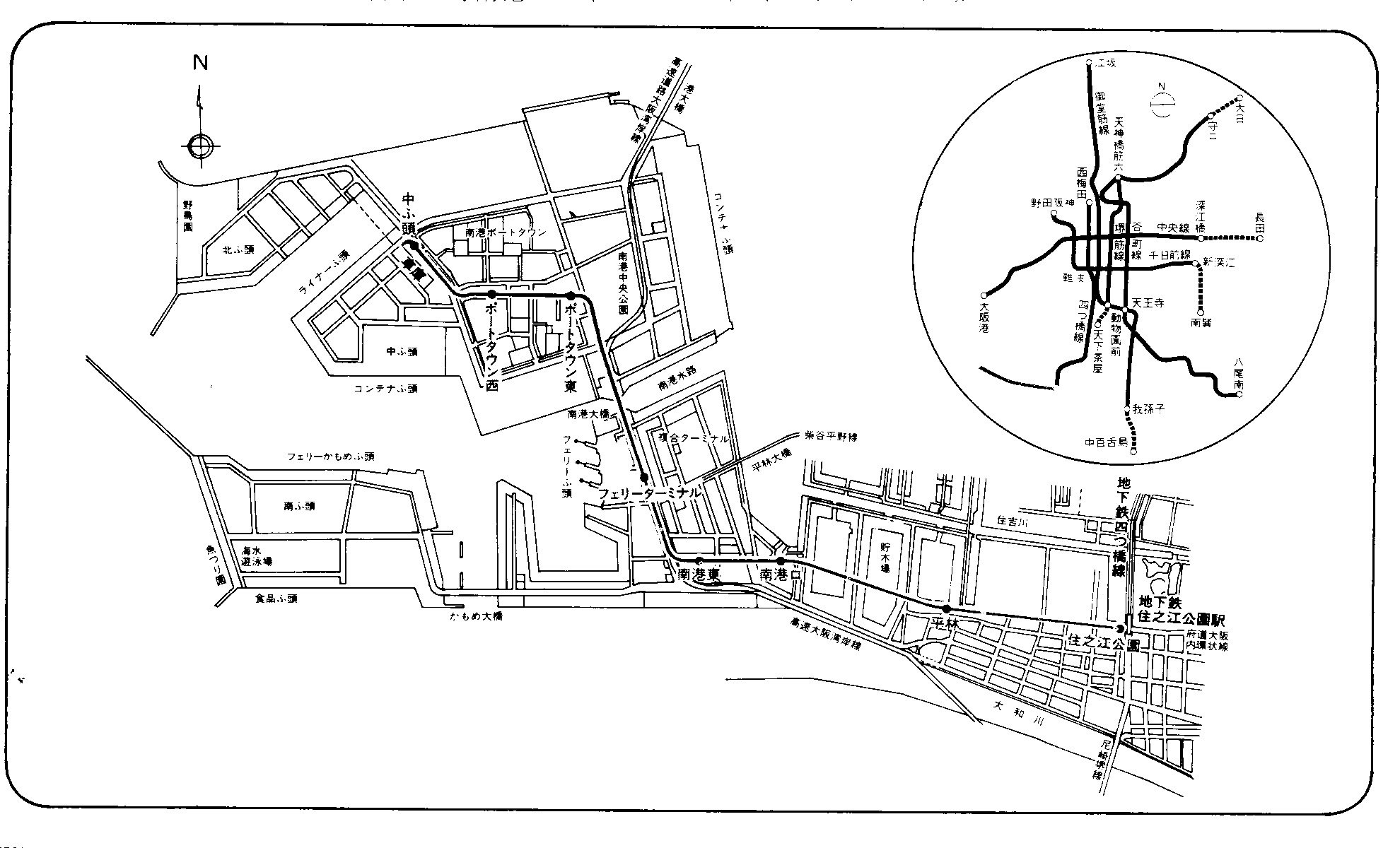
そして昭和53年3月にインフラ部の工事に着手して、5月26日に起工式が挙行された。その席上で、当時の大島市長は、この新交通システムの愛称を公募することを発表した。広く全国から10,274通の応募があり、審議の結果、昭和53年7月15日「ニュートラム」に決定した.
昭和55年5月20日に最初の車両が搬入されて、6月2日から一部区間での試運転を開始。9月26日からは全線に拡大した。
ポートタウン線の建設費
昭和52年5月特許申請時の建設費は260億円と見積もられ,そのうちインフラ部が12,695百万円(インフラ率48.7%)、インフラ外部が13,347百万円であった。昭和49年度に実施した調査の中で算出した建設費に年5%の物価上昇率を掛けて計算された。しかし、その当時は新交通システム対する設計基準などはなく、建設省、運輸両省の指導を受けながら、大阪市独自の新交通システムの設計指針を作成した。
すなわち、インフラ部については、設計基準は道路橋示方書を参考に高架橋の設計基準を策定。高架橋の最大幅員は車両メーカーの意見をもとに6.4mと決められた.また、設計重量はメーカーの資料を参考に1両あたり14tとした。
橋梁形式については、都市計画道路敷津長吉線上は合成桁方式、阪神高速道路大阪湾岸線との共架部とポートタウン内から中ふ頭駅まではPC桁を標準とした。
駅は、住之江公園駅〜南港東駅までは鋼構造、フェリーターミナル駅〜中ふ頭駅間はRC構造としていた。
一方、インフラ外部については、メーカーの資料を参考にしながら、大阪市交通局の主に地下鉄に関する資料をもとに算出した。
それが、完成後に精査された数値では、建設費の総額は419.3億円(建中利子を含む)にまで膨らんだ。そのうち街路事業の部分が243.1億円で、港湾整備事業の分は176.1億円である。それぞれについて44.9%が国庫補助の対象となるインフラ部に対する工事費(昭和52年度は37.87%)であるが、その総額は188.2億円である。それに対して、実際にかかったインフラ部の工事費は総工事費の47.7%に当たる196.4億円であったので、結局8.2億円がインフラ部工事費であるものの、補助対象外として事業者である大阪市交通局の負担ということになった。そして、インフラ外部の工事費はこの超過負担分を含めて217億円ということになる。
建設費の推移 単位:百万円
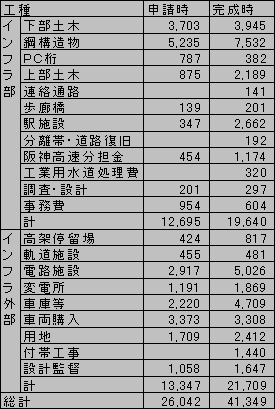
一方、財源については、この補助対象インフラ部の工事費である188.2億円のうち、2/3にあたる125.5億円が国庫補助され、残り1/2にあたる62.7億円が大阪市の負担となった。
インフラ外の工事費 231.1億円については、20%の46.2億円が大阪市の一般会計からの補助金が当てられた。残りは企業債を発行して調達されたが、企業債は財政投融資資金による政府資金のほか、市場公募債による民間資金が投入された.さらに、昭和52年7月26日関係5局長間の覚え書きで、企業債の元利償還が経営を圧迫することが見込まれることから、開業後に開発者負担金(他会計からの出資等の扱い)として総建設費の10%に当たる金額の企業債の元利支払い額を大阪南港の港湾運営特別会計からの繰入金で充当することになった。
建設費総額は、当初の計画段階よりも大幅に増加することになった。その理由として、インフラ部については、ポートタウン〜中ふ頭間をPC桁から合成桁に変更したこと。当初車両設計重量を1両あたり14tとしていたのを18tに変更したこと。全幅員を6.4mで計画していたのを7.4mに拡大したこと。および、当初インフラ外に計上していた駅の内装工事費をインフラ部に含めることになったことなどを挙げる.また、インフラ外部については、自動運転にともなう保安度向上のための施設の新設などで建設費が増加したが、計画両数を80両から52両に減らしたことで、自重の増加など設計変更で車両単価は上昇したものの、車両購入費が若干減額された。
その他、この新交通システム自体の事業費には含まれないが,関連して、住之江公園、フェリーターミナル、ポートタウン東の各駅にバスターミナルを整備した。その工事費が約6億円で、そのうちフェリーターミナル駅前のみ1億500万円の国庫補助を受け入れた.また、高架橋が建設された平面道路の補修に約2億円かかり、これは道路管理者である市が単独で負担した。
ニュートラムの開業
昭和56年1月17日営業開始認可を申請。1月31日には 旅客運賃制度の認可申請を行った.運賃制度、額ともに市営地下鉄と同じく決められ、対キロ区間制で、1区100円、1区増す毎に20円加算されるというもの.地下鉄との乗換は、通算制で一枚の切符で行くことができることになる。
そして、昭和56年3月16日13時に住之江公園〜中ふ頭間の運転を開始した。
開業後半月で40万人が利用、1日平均にすると25,000人ということになり、開業時に予想された旅客数4万人を大きく下回った。しかし、開業時の初乗り需要が集中する3月16日、17日と祝日・日曜日の21日、22日、29日には、昼間7分30秒間隔を5分間隔運転に増発。22日には1日46,000人の旅客数を記録した。さらに、3月26日からバス系統の再編を実施。新学期から高校生の利用が見込まれ、またポートタウンの入居者の増加で、利用客数が順調に伸びることが期待されたが、結局昭和56年度の平均は1日平均約20,000人にとどまることになる。
その後、南港ポートタウンの居住者が、56年3月の12,300人から61年1月には28,200人に増加。また、沿線への大学・短大の移転と高校の新設。さらに国際見本市会場・インテックス大阪の港区朝潮橋から南港中央埠頭へ移転や港湾関係施設の整備で、徐々に旅客数を増やして、昭和60年度には1日平均43,480人にまで伸びる。
そこで、昭和61年4月7日にはダイヤ改正を実施した.朝ラッシュ時と下校時の運転間隔を短縮するとともに、見本市開催時は平日8〜46本、休日34〜68本を大幅増発。とくに人気のあるイベントの開催日には、増発本数を平日54〜92本、休日78〜152本に拡大するというもの。
これにともなって車両を3編成増備。車両、検車場拡張など約10億84万円の投資となった。